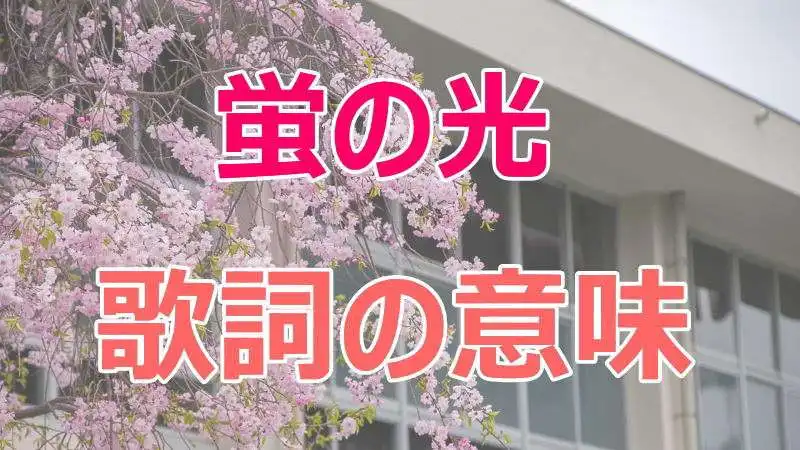「蛍の光」の歌詞の意味について、原曲と作詩者や歴史的背景を詳しく解説します!
卒業式では定番の蛍の光。
でもって、蛍の光の歌詞の意味について詳しく知る人は少ないかも知れませんね。
蛍の光は、もともと悲しい別れをテーマにした曲から歌詞が付けられました。
今回は、蛍の光の歌詞の意味について、原曲と作詩者や歴史的背景をまとめてみました。
「蛍の光」の日本語歌詞が生まれた歴史的背景
「蛍の光」の日本語歌詞は、明治時代にスコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」の旋律に基づいて作られています。
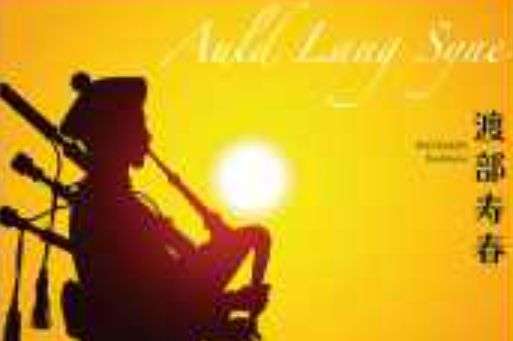
原曲は1788年にロバート・バーンズによって書かれ、友人との別れをテーマにしている、ちょっぴり悲しい物語。
日本においては、1881年に文部省唱歌として採用され、稲垣千頴さんが日本語の歌詞をつけました。
この歌詞は、教育の重要性と学問の励みを象徴しており、当時の日本の教育改革の象徴ともなっていました。
「蛍の光」歌詞の意味!1番~4番を解説
「蛍の光」の歌詞は、4つの段落から成り立っています。
1番の歌詞は、「蛍の光、窓の雪、書読む月日重ねつつ…」という出だしで、夜遅くまで勉学に励む学生の情景を描いています。
2番の歌詞は、「止まるも行くも限りとて…」と続き、学問に励む日々と別れの悲しみを表現しているのです。
3番の歌詞は、「いつしか年もすぎの戸を…」で始まり、戦争時の困難な時期を乗り越える決意を示しています。
4番の歌詞は、「天の光を身に受けて…」と結び、未来への希望と平和の願いを込めた歌詞となっています。
何とも壮絶で憂いに満ちた蛍の光…
「蛍の光」歌詞の意味と象徴について解説

1番、2番の歌詞の意味は学生の努力と別れ
1番と2番の歌詞は、学生が夜遅くまで勉強に励む姿と、学校生活の終わりに直面する別れの瞬間を描いています。
「蛍の光、窓の雪」は、暗い中で蛍の光や窓外の雪を見ながら勉強する様子を象徴しています。
「書読む月日重ねつつ…」は、日々の努力の積み重ねを示しており、学生たちの頑張りを強調しています。
2番の「止まるも行くも限りとて…」は、学校生活が終わりに近づいていることを表現し、友人たちとの別れの寂しさを描いています。
3番、4番の歌詞の意味は戦時中の状況と未来への希望
3番と4番の歌詞は、戦時中の厳しい状況とそれを乗り越える決意を描いています。
3番の「いつしか年もすぎの戸を…」は、戦争によって時が過ぎ、困難な時期を迎える様子を示しています。
また、「今日こそ身をも惜しまぬ」の部分は、国のために尽くす決意を表しているのです。
4番の「天の光を身に受けて…」は、戦争が終わり、平和な未来を迎える希望を歌っており、未来への期待と平和の大切さを強調しています。
このように、「蛍の光」の歌詞は、学生時代の努力と別れ、戦争時の困難と未来への希望を象徴する深い意味を持っています。
日本の教育と歴史における重要な歌として、今なお多くの場面で歌われ続けています。
「蛍の光」の歌詞と現代における意義

卒業式「蛍の光」の昔と今の歌詞の比較
「蛍の光」の歌詞は、長い間日本の卒業式の定番ソングとして親しまれてきました。
昔は、学び舎を離れる寂しさや友情の別れを表現するこの曲が、卒業生たちの心に深く響きました。
例えば、戦後の日本では教育の重要性が高まり、「蛍の光」はその象徴ともなっていました。
現在でも多くの学校で卒業式に歌われますが、昔とは少し異なる感情が込められています。
この変化は、時代とともに学生たちの価値観や教育環境が進化した結果と言えます。
閉店や閉園時の曲としての蛍の光
「蛍の光」は、最近では大きい店舗やテーマパークの閉店・閉園時に流れる曲としても知られるようになりました。
これは、来店客や訪問者に対して静かに退場を促すための手段として利用されています。
例えば、大型百貨店や遊園地では、閉店時間が近づくと「蛍の光」が流れ、訪問者に営業終了を知らせます。
この新しい役割は、もともとの別れの曲という意味を継承しながらも、現代の社会に適応した形で使われていると言えます。
「蛍の光」の歌詞に見る文化的意義とは
歴史的な背景と文化における役割
「蛍の光」の歌詞は、教育の象徴として日本の文化に深く根付いています。
明治時代に稲垣千頴によって作詞され、スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」の旋律に乗せて歌われるこの曲は、学問の励みや努力を称える内容で、多くの人々に愛されています。
例えば、明治時代から昭和初期にかけて、教育改革の一環としてこの歌が広まり、学生たちの心に深く浸透しました。
現代の使われ方とその社会的影響
現代においても、「蛍の光」の歌詞は様々な場面で使用されています。
卒業式や閉店・閉園時の他に、公式行事やイベントでも歌われることがあります。
こうした背景から、「蛍の光」は時代を超えて人々の心に残る曲となり、文化的な遺産としての価値が高まっています。
また、現代の社会においては、別れや新たな始まりを象徴する曲としての役割も担っており、多くの人々にとって特別な意味を持ち続けています。
「蛍の光」の歌詞の意味のポイントまとめ
「蛍の光」の歌詞は、明治時代にスコットランド民謡の旋律に日本語の歌詞を付けて作られました。
歌詞は学問の励みや別れを描き、卒業式や閉店時に使われるようになっています。
1番と2番は学生の努力と別れ、3番と4番は戦時中の困難と未来への希望を歌っています。
現代でも文化的遺産として、多くの場面で愛され続け、「蛍の光」の歌詞は、現代の社会においても重要な役割を果たしているのです。